あらゆるものは放っておくと、商業的になっていきます。
そして商業的になると、人はそれを敬遠する傾向があります。
その末路はサービスの破綻です。
こうしたことをネット上のサービスは過去何度も繰り返し経験してきています。
以前「mixi」という日本版SNSが隆盛を極めていた時期があります。
もしかしたら今の10代、20代の方は名前すら聞いたことがないかもしれません。
私の知る限りでは、SNSは元々アメリカに始まり(SNSの原型はFriendstar)mixiよりもFacebookの方が若干古い歴史を持つのですが(設立はどちらも2004年)、mixiは日本のSNSの先駆け的な存在として一斉を風靡しました。
今もmixiはありますし、ほとんどの人がアカウントを残したままの放置状態でログインをしなくなってしまったとは言え、まだ一部の熱狂的な信者ともいえる方達が利用するSNSとしてmixiはなお存在しつづけています。
UI(操作感覚)についてはmixiは当時の日本人の感覚にとてもあっていて、検索して簡単に昔の友達と繋がることができたり(久しぶりに小中学校の友達とネットを通して繋がれた時のあの喜びは本当興奮ものでした。「mixi、すげえな」と思いました。)、コミュニティ(部活のようなもの)を立ち上げてネット上のサークルのような感覚で集まったり、仲間内でやるにはいろいろと便利な機能が盛り沢山でした。
「あること」について興味がある人同士が集まったり、顔も知らない人ともコメントで自由にやりとりできたり友達になれるので、企業広告としてもターゲット選定をしやすく、理想通りに運用していくのであれば、これ以上ない、とても素晴らしいビジネスモデルだったと思います。
例えば、私のようにスキューバダイビングが好きな人が集まるコミュニティがあれば、そこに企業が広告をうてば、商品やサービスを興味がある人に向けて簡単にアピールすることができますし、アウトドアが好きな人だけが集まるコミュニティを立ち上げて、そこにアウトドア関連の広告を貼ればテレビCMのように不特定多数な人たちにではなく、マトを絞った効率的な広告運用ができるようになります。
広告を打つ企業側からすれば、それまでブラックボックスに包まれていたユーザーを可視化できるため、どのような人が、どのようなことに興味を抱いていて、どのようなことに悩んでいてどういう解決策を求めているのかがわかりやすいため、広告としての効果を期待しやすいのです。
これらは現在Facebookでもグループ作成機能として実装されていますが、日本人の感覚にあったドメスティックなメディアとしてのUIはmixiの方が遥かに上だったように感じます。
Facebookは私がアジアをいろいろめぐっていた時期に友人に勧められるがままに登録したのですが、記憶が正しければ当時は表記は全て英語で、操作方法も独特で、UIは日本人を意識したものとは言えず(単純に当時の私の感覚に合わなかっただけかもしれませんが)、操作方法がと〜っても面倒臭いものでしたから・・・。
・・・けれども2022年現在、mixiはまるで存在しなくなってしまったかのように身を潜め、それに関わる噂話などもまるで聞かなくなってしまいました。
私の友達もmixiをやり続ける人たちなんていませんし、mixiにいた人たちはこぞってFacebookに移行してしまっています。
商業的になるとやがて廃る
mixiが廃れた理由はそれこそたくさんあるかと思いますが、その大きな理由の一つに外部からの働きかけによりmixiが商業的になってしまったということがあげられると思います。
それがmixiの失敗の原因の一つだと、少なくとも私はそうみています。
例えばmixiは「あしあと」という機能が実装されており、誰がいつ自分のページを訪問したのか、わかるような仕組みになっていて、それがmixiの特徴の一つで当時のSNSとしては非常に画期的なものでした。
「あしあと」はLINEなどでいう「既読」に近いものとして感覚的に捉えていただければわかりやすいかと思います。
何分前に自分のページに訪問してくれたのかまでが分かるのです。
この誰が自分のページを訪問してくれたのかは内輪でやっているうちは、本当に楽しいもので、誰が自分の書いた「日記(ブログ)」を読んでくれたのかが感触としてわかるようになっていたため、ログインをしたらまずは「あしあと」を見るほど画期的な機能でした。
さらに、知らない人が「あしあと」を残してくれていたりすると嬉しいもので、どんな人が自分のページを閲覧してくれたのか、ログイン後すぐさまページを確認しに行ったものです。
ただ、その「あしあと」という機能は画期的な面もあれば不都合な面もいろいろあります。
商業的な色合いを持った業者にとってこれほど便利でおいしい機能はなかったからです。
たとえば、mixiにわざわざ高い広告費を捻出して広告を打たなくとも、特定の商品に興味を持ちそうなコミュニティから入り、「あしあと」を残しておけば、それだけで自分のページを高い確率で見てくれます。
それもFacebookのように実名登録ではなくmixiは匿名登録がよしとされていますから、1個人の立場としてステルス的にPRできるという非常においしい媒体であったのです。
それに、mixiにログインしたユーザーとしては、「あしあと」を残してくれた人物がどんな人物であるのか、プロフィールページを真っ先に確認するという流れをとりますから、そこに外部リンクなどを貼っておき、うまい具合に商品紹介ページに誘導すれば宣伝などしなくとも簡単に商品を販売することができます。
例えば、下記のような形です。簡単な自己紹介をした上で・・・
「私は兼ねてから性格が暗く顔もブサイクで恋愛に縁がなく悩んでいましたが、失敗を繰り返すうちにある方法を使えば誰とでも簡単に恋愛関係になれることがわかりました。今では私のような恋愛に悩んでいる方に向けてそれが成就するような活動をしています。そんな私の過去の苦い経験をまとめたものをこちらのページで公開しています。mixiでやると規約違反になりますので、詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください」
と言ったような形です。
上の文章はブラッシュアップが必要ですが、こんな一見すると嘘のようなことをプロフィールページに書いて、リンク先に貼っておくだけで、簡単に集客し売上をたてることができてしまっていたのです。
実際私の当時のビジネスパートナーはmixiの「あしあと」機能を利用して、めちゃくちゃ利益を上げていたこともあります。
訪問して「あしあと」をワンクリックで残しておくだけで、高い収益を獲得できるのですからこれほど素晴らしい方法はないと言っていたほどです。
しかも「あしあと」は無料です。
どんなにあしあとをつけても無料で特定のターゲットに向けて宣伝できるのです。その方法は至ってシンプルで特定の商品に興味がありそうな人物を探すためにコミュニティから入って、一人一人のページを訪問しあしあとを残しておくだけ。
当時のmixiはログイン率はそれこそ高いものでしたから、それだけで商品が売れていくという業者にとってこれほどおいしい機能はなかったのです。
しばらくすると自動で「あしあと」を残すための「自動あしあと残しツール」なるものも出回るようになりました。
ツールからログインして、設定しておくだけで、特定のコミュニティーのページ内を勝手に巡回してくれ「あしあと」を残してくれるというツールです。
わざわざ自分で訪問することがなくなり、「あしあと」を自動制御できるようになったのです。
こうなってくると、mixi内で本来の「あしあと」としての機能は、機能しなくなってしまいます。
だって、ログインしたら、「あしあと」が知らない人ばかりで、しかも業者ばっかりだったら嫌になるでしょ?(笑)実際そうなっていましたし。
mixi側もバカじゃありませんから、これに対して数々の対策を取るようになります。
例えば、1日につけられる、「あしあと」の数を制限したり、ツールを使うと自動的にログアウトするようにしたり、極端に「あしあと」を残した人は退会処分したりと言ったように数々の制限を設けていたように思います。
結局mixi側は、この「あしあと」機能に振り回されることになり、私の記憶が正しければmixiにとってなくてはならなかった「あしあと」がなくなったり、訪問したことがわからないように後から「あしあと」を消す機能が実装されたりといろいろと迷走していくことになります。
そうこうしているうちにFacebookにその座を譲られてしまったという感覚があります。
Facebookはこの点を「good」というボタンで実装し日本では「いいね」機能として認知されるようになりました。
放っておくとあらゆるものは商業的になっていく
放っておくと、あらゆるものは商業的になっていきます。
そしてそれが商業的になった時点で、それを運営側がうまくコントロールしないとコミュニティはすぐに破壊されてしまいます。
つまり過度に商業的になっていくと、サービスとしてのバランスが崩れ、人が遠のいていってしまうのです。
サービスをコントロールすることの難しさ
今でいうInstagramもだんだんとその色が濃くなってきているように思います。
はじめは内輪でワイワイやっていたのが、人が集まるとそこに商売は生まれるもので、だんだんと商業的な色合いが濃くなって、知らぬうちに企業広告が入り込むようになってきています。
それもInstagramの運営元に依頼しPR(広告)という形で広告を打つのではなく、ある程度フォロワー数をかせいでいて、影響力がありそうなインスタグラマーに企業側からオファーをし、時期を見て徹底的に紹介してもらうという方法です。
なかには詐欺的なものもあります。
いつの日も市場が熱狂すると、詐欺の発生率は上がるものだからです。
>>>市場が熱狂状態にある場合、詐欺の発生率と複雑性が急激に増す
以前からありましたが、コロナ禍になってその色は濃くなったように思います。
そうしてみると・・・やはり、Instagramもそろそろ終焉が近づいているような気がしてなりません。
やり方は違えど、本質的にやっていることはmixiと同じですから。
まだインスタグラムはSNSとして存在感を示しているように思えますが、企業広告ばかりが目立つようになってきてしまっており、そうした商業的な色合いを帯びてくると、人は敬遠していきます。
サービスを利用している、いちユーザー側からすればその人が言っていることが本当かどうかわからなくなり、見分けがつかなくなったり、広告に振り回されるようになり、だんだん辟易してくるのです。
つまり以前まであったサービスとしての信用度や信頼度がなくなってきてしまうのです。
これはネットに限ってのことではなく、世の中のあらゆるサービスを見ていると本当にそう思います。
特に、ネット上のサービスはそうしたコントロールが本当に難しい。ネット上のほとんどの無料で提供しているサービスは広告に依存しているという背景も原因としてあります。だから長く続くサービスというのはあまりありません。
サービスが有名になったり、火がついた時点でもう終わりが見えていると言ってもおかしくないほどです。


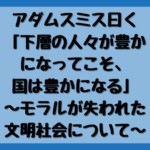
の基本的な使い方と記事執筆に役立つ13の操作-485x253.png)



ってなに?CVの意味や種類、計測法など徹底解説!-485x253.png)


コメントを残す